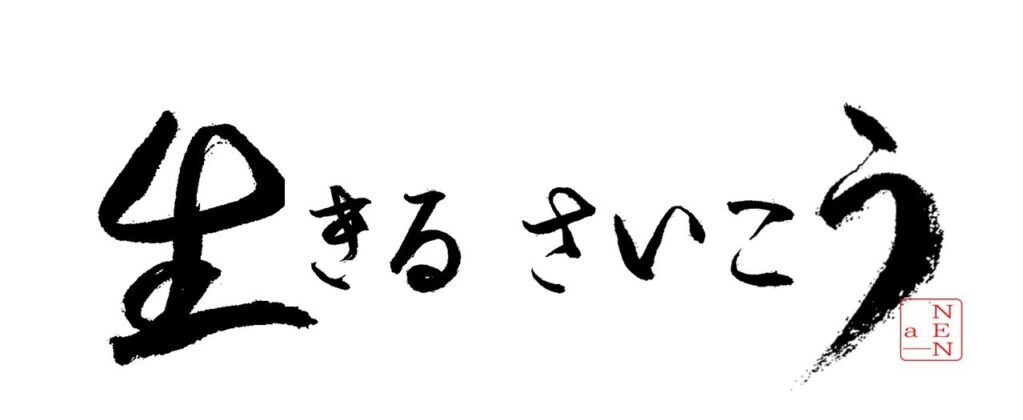★投稿修正★ 2025年2月3日 by a-NEN
今回のテーマは、奇抜で大胆ですヨ。私が、長年の鬼論争に終止符を打ちます!?[汗]
2月の節分を前に、鬼について考えます。
節分以外で、鬼と聞いて思い浮かぶのは、やはり、昔話の桃太郎や一寸法師でしょうか。それとも、アニメ鬼滅の刃でしょうか。私は、このアニメの影響で鬼への興味も湧いた程で、大のファンです。こころを揺さぶられる素晴らしい作品なので、世界中で人気があるのもうなずけます。
変な質問ですが… [いつも変な質問しかしませんが.笑]
みなさんにとって、鬼とは何でしょうか。
「私にとっての鬼?… ん? 」
ほとんどの方が、「鬼のことなんて考えたことがない」かもしれません。
また、「そもそも、鬼なんかいない」という方もいるでしょう。
はたまた、「鬼はいるけれども、自分とは関係がない」という方もいるかもしれません。

せっかくなので、まずは、節分と鬼について少し触れたいと思います。
節分とは、みなさんご存知、毎年2月3日頃に行われる日本の伝統行事ですよネ。本来、節分とは、四季が移り変わる節目という意味で、年に4回訪れる立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指すそうです。それが室町時代から、現在のように立春の前日のみを指すようになり、今のような豆まきの行事が始まったとのこと。(日にちは、毎年2月3日とは限らず前後します)
節目の時期には邪気が入りやすいと考えられており、旧暦でお正月にあたる立春は、日本では古来より特に重要視されています。節分は、1年で最も重要な立春の前日に、 “悪いものを追い出し、縁起の良いものを食べて新しい年を迎えよう”という意図で行われてきた行事です。
節分のルーツは、飛鳥時代から宮中で行われていた神事“追儺(ついな)”だと言われています。(『続日本紀』に追儺実施の記録あり) 追儺は、中国の宮廷で大晦日に行っていた鬼を追い払うための神事で、日本に伝わったものだそうです。鬼ごっこの起源となった鬼を追いかけ回す神事、桃の木で作った矢を射るといった神事など様々あり、その中の一つ、 “豆うち”の儀式が、豆まきの由来になったと考えられています。古くから穀物には霊が宿り、魔除けの力があるとされ、米などをまいた時期もあるようです。諸説あるようですが、魔の目(魔目=まめ)に豆をぶつけて魔を滅する(魔滅=まめ)という意味にも繋がることから、豆をまくようになったとも言われています。
節分において、 “鬼=邪気,魔”。 “鬼は、悪いものの象徴”ということです。
では、鬼の正体とは何でしょうか。
歴史を通して見てみます。
鬼という言葉は、中国から入ってきたそうです。漢字の“鬼”は死体を表す象形文字で、中国では、人は死んだら鬼になると考えられていました。鬼とは死者の魂で、良い鬼も悪い鬼もおり、姿形のないものとされました。日本でも、この名残があり、ごく最近まで、人が亡くなった時に病院のカルテに“鬼籍に入る”と記しているものもあります。
ただ、日本では、仏教の概念と結びつくことで、鬼は恐ろしくて怖いもの、悪しきものと捉えられるようになっていったようです。最初は、 “おに”という読み方もなく、鬼のような存在を日本では“モノ”と呼んでいた。怨念を持った霊や邪悪な怨念を意味し、実体のない存在と認識されていたようです。
“おに”という呼び名が定着していったのは平安時代のようです。仏教思想の影響で、鬼が、地獄の鬼のような実体を伴う恐ろしい怪物として認識され始め、物語などの中でも描かれるように。 “この世ならざるモノ”という意味の“隠(おぬ)”と呼ばれ、さらに“鬼(おに)”という名前へと変わったと言われています。

一般的によくイメージされる鬼の外見は、パーマをかけたような縮れた頭に牛の角を2本生やし、腰には虎の皮でできたパンツを履き、手に金棒を持った姿ですネ。これは地獄の鬼が由来となっているようで、風水と関連があるとされています。鬼が出入りすると言われる“鬼門”が北東とされており、昔の方角で北東は「丑寅(うしとら)」の方角。そこから頭が牛で下が虎という鬼の姿が生まれたとされているようです。
■定まった姿のない妖怪としての鬼
昔話や民間伝承に登場する鬼の多くは妖怪です。疫病、自然災害(干ばつ、洪水、大地震..)、不作などによる飢餓が人々を苦しめてきました。未知の自然現象や未確認生物などは、妖怪だと考えられていたようです。人を取って喰うなど、人に害をなし恐怖を与える存在として信じられ、おどろおどろしい気配を秘めた、得体の知れぬ恐ろしい化け物として様々な姿で描かれています。妖怪として鬼は、人の理解を超える超科学的な奇怪で異常な現象や、それらを起こす不思議な力を持つ非日常的・非科学的な存在として位置づけられます。
妖怪とは、 “何かわからないモノ”への漠然とした恐怖が生み出した存在であるとも考えられます。
妖怪の存在を信じるみなさまから、お叱りを受けそうですが…[汗]
妖怪がいないという証明もないので、いる可能性ももちろんございます。
妖怪を身近で親しみのあるものとして、現代の世に広めたのは、漫画家の水木 しげるさんではないでしょうか。水木さんの作品からは、世の中の全てのモノや現象に対する畏敬の念(リスペクト)と妖怪との共存というメッセージを感じます。また、妖怪は、人のこころの写し鏡として描かれているように思えます。
■神としての鬼
鬼は“神”に通じているという捉え方もあるようです。古代の人は、あらゆるものに神や精霊が宿ると考えており、目に見えないものや人の理解を超えた存在があることを、自然に受け入れていました。そのため鬼は、山や土地を守る神々を指し示すことがあったようです。確かに、鬼を祀っている地域もありますネ。
古来より絵巻や能でも表現されていますが、この世界観を、現代で美しく表現しているのが、もののけ姫,となりのトトロを代表とするスタジオジブリ作品ではないかと思っています。
神としての鬼は、前述の妖怪としての鬼と同じような感覚ではないでしょうか。
■仏教の中の鬼
仏教では、六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天道)と呼ばれる6つの世界が存在します。亡くなった後に、前世の行いによって決まる来世で生きる世界のことです。その中の“餓鬼道”と呼ばれる世界に生きるのが、鬼の一つである“餓鬼”です。餓鬼は常に飢えに苦しみ、食べ物と水を手にしても火に変わるため、決して満たされることがないとされています。前世で金や食べ物を独り占めした欲深い人間は、この餓鬼に生まれ変わってしまうそうです。 “地獄道”に生きる鬼もおり、六道の中で最も辛く苦しい世界で、前世で人殺しのような悪事を働いた者が落ちる場所とされています。
また、仏教における5つの煩悩のことを五蓋(ごがい)といい、その五蓋を鬼の色に当てはめて、戒めとしています。
赤色の鬼が表す煩悩は“貪欲”。貪欲とは、人間の欲望。
青色の鬼が表す煩悩は“瞋恚(しんに)” 。瞋恚とは、怒りや恨み、憎しみといった人間の憎悪の感情。
黄色の鬼が表す煩悩は“掉挙・悪作(じょうこ・おさ)” 。掉挙・悪作とは、浮ついた心や甘え、執着など、自身の心の弱さ。
緑色の鬼が表す煩悩は“惛沈・睡眠(こんじん・すいめん)” 。惛沈・睡眠とは、やるべきことをやらない、だらだらと眠ってばかりいるというような怠け心からくる不健康や不摂生。
黒色の鬼が表す煩悩は“疑惑(ぎわく)” 。疑惑とは、自分や他人を疑う心、愚痴、自身の中にある不平不満の心、卑しい気持ち。
五蓋を見ていると、ドキッとします。[汗]
■未知なる人を指しての鬼
日本書紀に、遠い国からきた外国人や海賊,山賊などの反社会的集団を“野蛮で醜いモノ”という意味で“鬼魅(きみ・きび)”との記述があるそうです。 “おに”という読み仮名も振られており、自分たちには“未知で得体の知れないモノ”を総称して鬼と呼んだと考えられています。
■差別としての鬼
昔、体の形状に異常のある子は、 “鬼子(おにご) “とされ、捨てられることもあったようです。外見に恐れを抱き、不吉なことが起きる予兆として、育てることが難しい子を鬼とみなすことによって排除していました。
また、家父長制の浸透とともに進んでしまった女性差別により、鎌倉,室町時代と時代を下るに従って、女性が鬼のイメージと結び付けて描写されるようになったようです。能でも、嫉妬に狂う女性の鬼が多く登場します。確かに、般若のお面は女性です。
さらに、明治時代以降、鬼は戦争と結び付けられ、外国人を鬼としています。日露戦争では桃太郎が、露西鬼(ロスキー)を征伐する絵本が描かれ、太平洋戦争では、鬼畜米英として、米兵、英兵が倒すべき鬼となりました。
障がい児も女性も外国人も、恐れを抱く存在だったからこそ、鬼と同一視されたと考えられます。
【リンク:「鬼とは何者か―差別、偏見、排除の日本史」■サイト名「公益財団法人ニッポンドットコム」さん】
■悪霊としての鬼
霊的な存在として現れる鬼の正体は、人間自身。人が怨念や嫉妬などによって悪霊となり、鬼の姿へと変わるとされています。つまり、人が生きながらにして鬼に化けるというものです。悪霊であるため、妖怪の鬼と同様人に災いをもたらす恐怖の対象として扱われています。悪霊は、能などでも表現されています。
人のこころが関係しているというところで、仏教の五蓋との関わりが深そうだと考えています。この世界観を見事に表現しているのが、鬼滅の刃 だと思っています。登場する鬼は、元々は普通の人で、不遇に飲み込まれる中で鬼となっています。主人公は、鬼の悪行自体は許さないのですが、鬼を倒した際には、優しく弔います。また、主人公の妹は、鬼に襲われたことで鬼と人間が混じった状態です。鬼と人との境界線がはっきりとしない、混ざりあっている世界を描き、誰もが鬼と化してしまう危険性があることを示しているように感じます。
「私はなにか善を行おうとする希望を持ち、そこに悦びを感ずることもできる。だが同時に、悪を行いたいとも思い、そこにも悦びを覚えることができる」
フョードル.ミハイロヴィチ.ドストエフスキー(小説家,思想家)
鬼の正体をまとめると…
鬼とは
●得体の知れないモノ、恐れているモノを指す
●定まった姿形はなく、様々なモノがある
●人が存在の意味を定めており、その時代により変わったりしている
●人のこころとの関係性が深いモノ
では、はたして、鬼はいるのでしょうか。
先に結論から言うと、「鬼はいるのか、いなのか、はっきりしない」というのが、一般的で間違いのない答えでしょう。事実、鬼がいる(いた)という証明も、いないという証明も、誰もできていませんし。[当たり前や。汗] こんなことを言うと、鬼伝説が残る全国各地のみなさまから、お叱りを受けそうですが、白黒よりも、ロマンそのものの方が大切ですネ。
では、私の結論です。「鬼はいると思えばいるし、いないと思えばいない」。
付け加えて言うと、「各自の認識次第で、いるか、いないかが決まる」と考えています。
そして、私のオススメは、「各自で自分なりの鬼を設定しておく」というものです。
なぜなら、私たちの世界には、目に見えないモノも多く、また、知らないことも無数にあるからです。また、私たち個々の存在や力は、宇宙の中では、偉大でもありながら同時に、ちっぽけなモノでもあるからです。 “得体の知れない、恐れるモノ”を正しく持つことで、人としての適切な謙虚さを保つことができると考えています。科学で解明されていないことも多いので、正確には“非科学ではなく、未科学”と言った方が良いでしょう。
私の考える鬼とは、外なる鬼と内なる鬼です。
外なる鬼とは、自分の外からやってくる自然災害や疫病などの予期せぬ災禍(さいか)のこと。どれだけ科学が進歩しても、予測もコントロールもできないことは数多くあります。水害、地震、新型コロナウィルス、不慮の事故などはこれです。もし、悪霊や悪魔に取り付かれるという現象があるとするならば、不慮の事故に属するかもしれません。外なる鬼が、いつ誰の身に降りかかるかは、誰にも分かりません。“祟り神”とどのように向き合うのかということでしょう。
自然や神仏などに対する敬意を込めた“畏れ”と心配や不安の“恐れ”を適度に抱き、謙虚に生きる心構えと日々の備えが、幸せに生きるために大事なことだと思います。

内なる鬼とは、自分自身の欲やこころの弱さのこと。仏教の五蓋とも重なります。欲に溺れる、怒り、嫉妬、孤独、不安などでこころに魔が差した時に、悪の世界に取り込まれることがあると思っています。自らこころのコントロールを失い鬼となる(自分から鬼になる)場合、他人に引きずり込まれて鬼となる(鬼に襲われて鬼となる)場合があると思っていますが、いずれにせよ、自分自身のこころの問題です。
「誰が鬼で、誰が鬼ではない」「鬼はまわりにおり、自分は絶対に鬼にはならない」という感覚は危険だと考えています。世の中に、絵に書いたような、分かりやすい鬼はいないし、善人と悪人とではっきりと色分けされている訳でもありません。善人の中にも悪があり、悪人の中にも善がある。自分の中にある善悪はグラデーションとなっており、悪の部分が勝った時に鬼となる。長時間、鬼が占めると、完全に鬼と化してしまうのではないでしょうか。
私も含め、全ての人が鬼の芽を持っているのではないかと考えます。その芽を無くすことは難しく、芽を認識すること、上手くコントロールすることがカギとなるでしょう。ある時は、こころに結界を張る必要があるかもしれないし、入り込んだ魔を封じ込める必要があるかもしれません。自分の内にある鬼を外に出さないと、福を招き入れることはできないのかもしれませんネ。
自分の内なる鬼は、認識ができないと、手の打ちようもありません。自分のこころの動きやまわりの反応に気を配ることが大事です。何にこころを乱されているのか、原因は何か、自分の言動に対してまわりがどんな反応をしているのか… 自分が鬼と化していれば、自分で気づくことも難しいかもしれません。そんな時は、親しい人からの声に耳を傾けましょう。
もうひとつ気をつけておきたいのは、 “人の鬼は、私や社会がつくり出している部分もある”ということ。人を追い詰めたり、異質だと排除したりすることで、孤独や不安、怒りなどを増幅させ、鬼になる以外の選択肢が見いだせなくなってしまうこともあるのではないでしょうか。無差別に殺傷するテロや反社会的行為をする者の一部は、大人になるまでに不遇な環境で過ごしていることもあり、この構図で生み出されていると考えます。誰かが、どこかの時点で、手を差し伸べることができれば、もしかすると…
犯罪者が社会復帰した際にも、再起のチャンスがなければ、負のスパイラルは続きます。過ちは誰もが犯しうるのです。罪を憎んで人を憎まず。←罪が大きいほど難しいですが…
「善悪は人にあらず自らの心にあり」
錦文流(作家)の言葉?
鬼とは、自分の肉眼では確認できないモノ、自分で感じるモノ。
鬼は、私たち一人ひとりのこころの中にもいるモノ。
「鬼は~外、福は~内」
みなさんにとっての鬼とは、何でしょうか。
やる気がアップしますので、ぜひ、時々、上の2つをクリックしてやって下さい!