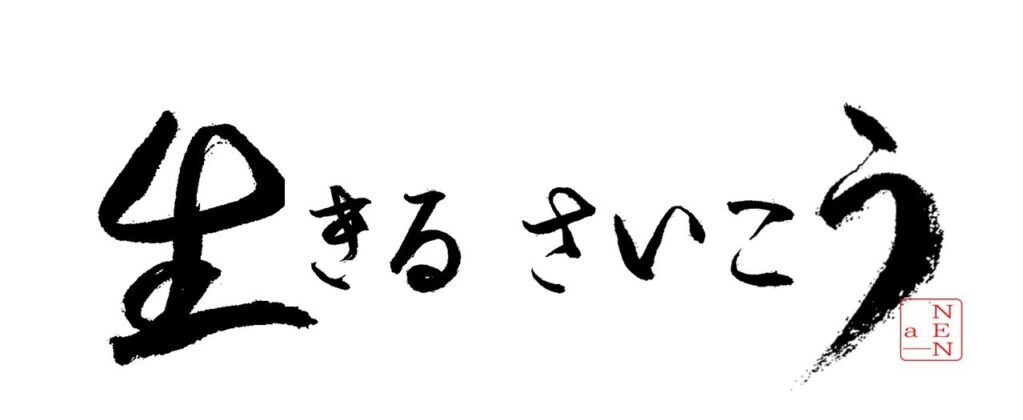★投稿修正★ 2025年11月2日 by a-NEN
あなたは、相手のことを簡単に許すことができますか。
事の重大さによっても異なりますが…
相手を許すことは、大事だとは分かっていてもなかなか難しいですよネ。
そもそも“相手を許す”って、何なのでしょうか。何だか上から目線な感じがして、違和感があるのは私だけでしょうか。
私は私、相手は相手。
私と相手は、対等な関係であるはずなので、相手からすると、私が許すも許さないも知ったことではない気もします。
相手との間に、境界線があることを認識する
私と相手とは別人格なので、例え似たもの同士であったとしても、同一になることは不可能です。お互い、相容れないこともあるのが自然です。まずは、自分と他人とを区別し、私と相手は違うのだという事実を受け入れることが肝心だと考えます。区別をするということは、自分というモノ(自分の信じる価値基準)を持つということでもあります。そして、相手の価値観や生き方も認識をして、どちらも尊重するということです。
私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。
私はあなたの期待に応えるために生きているのではないし、あなたも私の期待に応えるために生きているのではない。
私は私、あなたはあなた。
もし縁があって、私たちが通じ合えるのならそれは素晴らしいことだ。
たとえ、通じ合えなくても、それはそれで素晴らしいことだ。
私とあなたが私たちの基本、二人が一緒なら世界を変えていける。
フレデリック.サロモン.パールズ(医師)
相手と適度な距離を保つ
明らかに相手が悪い場合、(私も悪いが)相手も悪い場合もあるでしょうから、相手が許せないことも当然あります。
相手への怒り,私の苦しみが増す前に、相手との適度な距離感を考えてみましょう。
相手が許せない時に、私が取れる行動は次の2つのうちのひとつ。
相手を受け入れるのか、相手を拒絶するのか。もっと踏み込んで言うと、相手との関係を切らずに歩み寄るのか、相手との関係を切るのかとも捉えることができます。
① 物理的に距離を置く
甚大な危害を加えてくる相手の場合は、相手との関係を断ち切ることを自分に許しましょう。自分自身への優しさが第一ですので、まずは自分の身を守ります。仏教の教えでも、付き合ってはいけない人(例えば、他人に求めるだけで与えない人など)は遠ざけることを勧めています。関係性を壊さないことだけが正しいと思い込まず、この絶縁という選択肢も持っておきたいものです。(常にこの選択肢も頭にあると、気が楽です[笑])
また、関係は切らないまでも、できるだけ会わない,一緒にいないという環境を作る方法もあります。
② こころの距離を置く
相手の言葉を受け止め過ぎない (真面目さを緩める)
言葉は伝達の道具に過ぎません。相手のその話を聞くことは本当に大切なのでしょうか。いつも、真に受けるのではなく、気楽に捉えるくらいの方が健康的だといえます。相手から投げられた不快な言動も、受け止めはしても、受け取らないというのが賢い対処。受け取らなければ、腹も立ちませんし、相手の言動の答えは相手のところに残ったままです。例えば、悪口は、応酬しても火に油を注ぐだけで得るものはありませんので、打ち負かすのではなく、聞き流すのが得策です。
相手に共感し過ぎない (良い格好ばかりしない)
相手のその気持ちや考えに、どれ程の価値があるのでしょうか。共感する必要性があるのかどうかも考えてみましょう。自分の価値観と相容れない時は、合わせる必要はないと思います。無理をすると、自分が窮屈になり、自分らしい生き方ができなくなります。
相手の期待に応え過ぎない (期待を手放す)
相手のその期待に応えることに、どれ程の価値があるのでしょうか。自分が振り回されなければならない程の価値があるのかどうかも考えてみましょう。
相手の話を聞くこと,共感すること,期待に応えることも大事ですが、大事にし過ぎるあまりに、聞き過ぎ,共感し過ぎ,期待に応え過ぎという事態に陥ってはいないでしょうか。
「相手を気分よくさせるために、自分が不愉快な思いをする必要はない」
ジェリー.ミンチントン(作家,実業家)
相手の言動に期待し過ぎない (期待を手放す)
これは、怒りとも関係しますが、期待し過ぎて、期待が裏切られるとショックが大きくなります。それほど期待せずに待っていて、期待通りになればラッキーと思えるくらいがちょうど良いといえます。
相手の生き方や幸せに関心を持ち過ぎない (感情移入を緩める)
相手がどのように生きるのか、何に幸せを感じるのかは、相手の勝手です。本来、私たちは、相手に干渉する筋合い(権利)はありません。“人生における主語は私しかない”ということ。「私は◯◯だと思う」という言葉を相手が受け取るかどうかは相手が決めるものです。主語をあなたやみんなにしてしまい、「あなたは○○だ」「みんな○○だ」と言ってしまうと、押し付けとなり、ややこしくなります。
相手の言葉を受け止めたり、共感したりすることも大事ですが… 何事も“過ぎない”ことです。
相手を許す前に、怒り,苦しみと向き合う
相手が許せない時、怒りと苦しみが生まれます。
まずは、“怒り”について考えてみましょう。
怒りが生まれるメカニズムを、アンガーマネジメント協会では以下のように説明しています。
『怒り=A.コアビリーフが裏切られる ✕ B.マイナス感情,マイナス状態』
解説をすると、
A.コアビリーフとは、“こうあるべき”という自分が信じている考え,自分の常識(思い込み)のことです。これは、自分のこだわり所であり、自分らしさでもあります。
【コアビリーフの例】
真面目にするべき、正しいことをするべき、他人への迷惑を考えるべき、全力でするべき、白黒はっきりするべき、効率よくするべき、失敗は繰り返さないようにするべき、我慢するべき、弱音や不満は言わないようにするべき、嘘はつかないようにするべき、頼まれたら断らないようにするべき、縁は切らないようにするべき…
B.マイナス感情とは、不安,苦しみ,辛さなどの感情。マイナス状態とは、ストレス,不健康,空腹,寝不足など心身が良くない状態のことです。
コアビリーフが裏切られるという火花に、マイナス感情,マイナス状態というガスが合わさることで怒りという炎が生じるという、分かりやすい例えだと思います。どちらかをゼロにするか、どちらかをできるだけ小さくすることで、怒りを回避したり、怒りを小さくしたりすることができそうです。コアビリーフを手放すか緩める。心身を健康に保ち、良い気分でいる、ストレスや不満を貯めない…
この掛け算の違いが、怒りやすさの個人差と解釈できます。確かに、世の中には、よく怒る人とあまり怒らない人がいますよネ。
では、怒りとは無くせるモノなのでしょうか。また、怒ることは悪いことなのでしょうか。
怒りは、防衛感情と言われ、外部からの脅威や危険から身を守るモノのようです。つまり、人間にとってなくてはならない感情ということであり、怒らないということは不可能なのです。無くそうと努力することも間違いのようです。怒りを無理に押し殺すと、怒りが自分に向い、自分を責めたり、自己嫌悪になったりします。ひどくなると、こころの病気にもなります。
怒りと上手く付き合うための第一歩は、自分の怒りを認めることです。そして、“怒る時にはきちんと怒る”。怒り方の工夫が必要なのであり、怒ること自体は悪くないのです。
また、自分が傷ついた際、責任をすべて自分だけで負う必要はありません。自分の怒りの気持ちも尊重し、相手が許せないという自分自身を許してあげましょう。
●許せない相手に対する自分の気持ちを素直に吐き出します。
気持ちを相手にいきなり伝えるのではなく、一旦、紙に書き出すのが良いようです。(可視化すると感情が把握しやすい) 書き終えたら、その紙をゴミ箱に捨てます。(捨てると感情が手放しやすい)
「自分の感情は自分の責任。他人の感情は他人の責任」ジェリー.ミンチントン(作家,実業家)
ただ、怒りは、相手も自分も、互いの関係性も破壊してしまうモノでもあるので、振り回されずに上手く付き合うことが大事です。(どのようにコントロールし、言動としてどのように表出するか) 怒ると視野も狭くなり、ものごとの多様な面も見えなくなります。今、私たちに足りないのは、適切に怒るという考え方と技術です。
※怒りを客観視し、感情的にならずに、自分の思いや要望を相手に上手く伝える『アンガーマネジメント』という技術がありますので、興味がある方は、お調べ下さい。
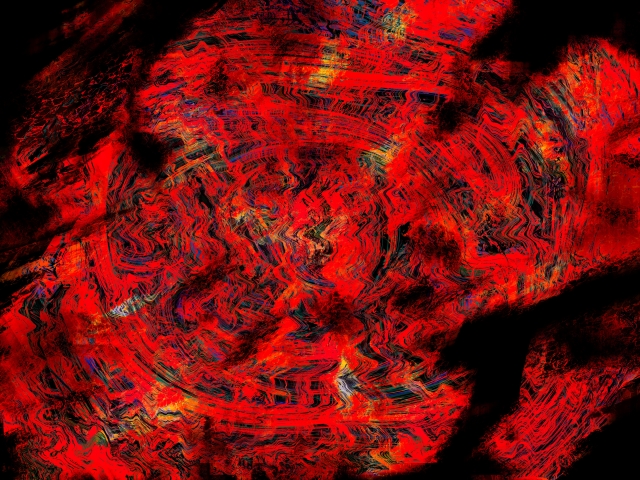
次に、私たちを悩ます“苦しみ”について考えてみましょう。
宗教も心理学も同じ結論に至っているのですが、苦しみとは、「現実」と「自分の勝手な思い込み(願望)」との間にあるギャップ(隔たり)によって生まれるということです。
何事も自分の思い通りにしたいという欲がありますが、思い通りにいくことはそう多くありませんよネ。私の人生の主人公は私ですが、相手の人生の主人公は相手です。世の中は、皆と共に生きている訳でもあり、摂理もあるので、当然ながら、私のルールブックどおりに物事は進みません。苦しみとは、いくらでも湧いて出てくる仕組みであるということを知っておいた方が良いでしょう。仏教で説かれている『諸行無常』、『愛別離苦』などはとても参考になります。【関連記事 ●安らかなこころへ、孤独から始めよう】
自分の力で、現実と願望のギャップを埋めることができるのかどうか。意味のある悩みなのか、意味のない悩みなのかなどを見極めることも重要です。意味があれば、向き合って乗り越えられるよう努力する価値もありますが、意味がなければ捨てる方が得策でしょう。
本来、事実というのは1つなのでしょうが、主観(自分ひとりのものの見方,感じ方,考え方)と客観(誰が見ても同じ認識となる事実や現象)とを区別するために、主観的事実と客観的事実と表現することがあります。主観的事実とは、私にとっての事実。客観的事実とは、第三者(私と相手以外の者)から見た事実。
“人生における現実(出来事や人間関係)は、私のこころを映し出す鏡”だと言われます。私が認識している世界は、私の主観によるものだから、当然といえば当然です。出来事の意味,自分が感じたことは、自分というフィルターを通してしか理解できないのです。以前、『3秒で幸せになる方法』という投稿でも触れましたが、“出来事の意味づけは自分自身でしており、そこに感情が芽生える”のです。禅語で、『一切唯心造(いっさいゆいしんぞう) 』という言葉があります。“この世のすべての存在や出来事は、自分の心が造り出したものである”という意味です。仏教の教えでは、外部の状況や環境が変わらなくても、心の捉え方を変えることで、経験する世界が大きく変わるとされています。出来事の捉え方や感じ方は、人それぞれで違い、自分自身においても成長過程で変化していきます。
『怒りや苦しみは、誰もが感じるモノで、どう向き合うかが重要。』
『怒りも苦しみも、他人や環境からもたらされるモノではなく、自分の中で作り出されるモノ。』
『怒りも苦しみも、“自分の思い込み(信念,常識)”が関係しており、生み出される大元は“執着”。』 相手への執着.自分への執着。
“執着を上手く手放すことができるかどうか”が鍵となりそうです。
許せないという感情は、相手への執着,自分への執着
許せないという感情は、相手の愛情,期待への裏切り、相手への嫌悪などから生まれます。裏返すと、自分の言動や存在を相手に認めてもらいたいという欲が、相手への執着の正体であると考えることができます。執着が強すぎる人は、相手との同一化(一体化)を求めているのかもしれません。
相手を許すとは、何も、相手の言動を肯定したり、認めたりすることではありません。キリストの教えにも、許せない行為を大目に見るということはないとあります。
私ができることは、その件から手を引くことです。“過去に起こったことは、もう変えることができない”という現実を受け入れるのです。腹立たしいという自分の気持ちを尊重しつつ、良い意味で相手や起きた出来事を諦めるということです。そうすることで、私たちは怒りや後悔から自由になれます。
許してしまうと、自分が損をする,自分が負けたような感じがするという方もいるかもしれませんが、本当の意味で何が損得、勝ち負けなのか捉え直すべきです。怒りを持ち続けることは、とてもしんどいこと。エネルギーも時間も相当に消耗します。いつまでも執着し過ぎている方が、損をし、敗北感も増幅させます。意識を切り替えて、今の自分にできることを考え、行動する方が建設的です。
doing(行い)とbeing(存在)という捉え方があります。相手が許せない時に、相手の行いが許せないのか、相手の存在そのものが許せないのか。どちらに焦点が当たっているかで、捉え方,自分の行動が変わります。存在そのものが許せない場合は、相手との関係性を見直すことも必要でしょう。相手を許すということは、相手を信じることであり、また、相手の存在に敬意を払うということかもしれません。
自分への執着とは、自分への愛着や自分のプライド(誇り,自尊心,自負心)へのこだわりです。結局これも、相手や環境を通して、自分がどう感じたかということです。自分がまわりからどのように扱われたか、自分が認められたのか、蔑ろにされたのか。その時、何を感じ、自分への愛着やプライドにどんな影響があったのか…
愛着やプライドは無さ過ぎるのも良くありませんが、有り過ぎるのも良くありません。私は、有り過ぎに要注意です[汗] 独り善がりになる危険性があり、人間関係に悪影響を及ぼすと、結果、自分を追い詰めることとなります。
許すとは、現実を受け入れ、執着を手放すこと。
やすらぎとこころの自由を手に入れるために、できるだけ上手く、相手や自分への執着.固執を手放そう。覚悟や勇気を持って、相手のためだけではなく、自分自身のためにも許そう。
相手とどのように向き合うのか、自分とどのように向き合うのか
物事を判断する時、自分の価値基準に軸足を置くのか、相手の価値基準に軸足を置くのか。別の言い方をすると、自分の物差しで相手を判断するのか、相手の物差しで自分を判断するのかということです。立場によって、事実の捉え方は変わります。相手には相手の事情があったのかもしれませんし、その相手の気持ちを考えることができていない場合もあるでしょう。私が、どこの部分に光を照らすかで、捉え方や言動が変わります。
私の感じ方,考え方や言動は、絶対的に正しいと言い切れるでしょうか。実際のところは、何が正しいのかすらはっきりとしないことも多いのでないでしょうか。
相手が間違いを犯すこともありますが、同じように、自分も間違いを犯すことがあります。
『私も相手も不完全で未熟な存在』
至らなさは、双方にあるということを肝に銘じるべきです。自分が他人に許されてありがたく思うのであれば、同じように、他人の間違いも許すべきでしょう。
そして、相手の身になって、相手の気持ちを想像することが大事です。
●許せないと思った相手の行動を書き出します。そして、相手の動機を想像して書き出します。また、相手の未熟さ,弱さ,不器用さについても考えます。
●相手に対して感謝できること、あれば謝りたいことを書き出します。
●その時、学んだことを書き出します。
●自分の思いや気づきを相手に直接、伝えることができそうなら、勇気を出して伝えてみる。
こころが整わず、まだ、相手が許せないということもあります。その場合は、まだ無理に許す必要はありません。焦らずに、傷ついた自分を受入れ、許せる機会が来れば許しましょう。
そして、もし、自分が間違いを犯した時は、不甲斐のない自分自身を許してあげましょう。間違いをしてしまったという結果よりも、その後の“自分がどう変われたのか”の方が大事です。償いは、誠意を尽くすことしかありません。私の誠意をどう受け取るかは、相手に委ねるしかないないのです。
作家で経営コンサルタントであるスティーブン.リチャーズ.コヴィーさん提唱の『インサイド・アウト』という捉え方があり、とても参考になります。【関連記事 ●3秒で幸せになる方法】
結局、自分が影響を及ぼせるのは、自分自身のことだけということ。つまり、自分で確実に変えることができるのは自分の言動だけということです。相手のしたこと,しなかったことを見るよりも、自分のしたこと,しなかったことを見る方が、実りがあるといえます。
怒りや苦しみが襲ってきた時は、何か大切なことに気づくチャンス,自分が成長できるチャンス。
今、自分が悩んでいる人間関係の問題の原因が自分自身にあることも多々あります。許せない相手が、かつて私に対して行っていた言動と同じことを、今の自分がまわりにしてしまっているということもよくあります。どのような考え方で、どのように接すれば良いのか。大事なことは、自分を見つめ直すことです。
人生とは、自分のコアビリーフを見つめ直すという戦いでもあると感じます。コアビリーフは、修正できる部分が常にあるのです。私は、コアビリーフというモノの捉え方を知るまで、自分のそれをあまり見つめ直したり、変更したりできずにいました。長らく修正を怠ってきたために、成長の幅,人生を楽しむ幅も狭めてしまっていたと気づきました。
自分が無知であるという謙虚さとコアビリーフを修正する柔軟性が必要だと痛感します。そして、自分の思い込みや執着に気づくために、自分自身の内面をよく観察すること。そのために、他人の話しや意見を聞き、良い部分を取り入れることです。
私の変えるべき部分はどこか、変えずに残しておく部分はどこか。少し崩しては、新しいモノを付け足し、そして少しずつでも成長をしていきたいのです。
『私と相手は、完全に同じにはなれない』
同じような部分だけではなく、違う部分も楽しめるようになりたいですネ。

『私も相手も、不完全で未熟』
お互い、許したり、許されたりしながら生きています。
相手を許すということは、相手に縛られないこと。相手を信じ、敬うこと。
自分を許すということは、自分の至らなさを許し、自分の信念に縛られずに自分を緩めるということ。
「許す」とは、最終的には、自分自身のために行うことです。
許すか否かは、自分の判断次第であり、自分次第でどのようにでもできます。
私は、許すことができるだろうか。
やる気がアップしますので、ぜひ、時々、上の2つをクリックしてやって下さい!